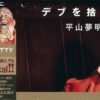『一流の育て方』から学ぶ!子どもにとって一番大切なことはモチベーションを授けること。
このブログでも、何度か悩み考えたこともある【子どもの習い事問題】。
小学校に上がり、明らかに毎日のタスクが増えてきた娘ですが、どうやら習い事を辞めたいようなのです。
今日は子どもの習い事問題を再び考えてみようと思います。
過去記事
子どもの習い事は誰のためか?大切なのはモチベーション。
そろそろ真剣に考えなきゃいけない時がきました。
仲の良い友達と一緒だからという安易な考えで始めた習い事には、その意味をちゃんと見つめなきゃならないし、これから始める習い事には本人の財産にするつもりでいくべきです。
と、親の心は決まっていても当の本人がその気になれないのならどうにもなりません。
だいたい親の心子知らずという言葉があるくらいですから、こういう大人になって欲しいなーという親の期待もまた伝わりにくいものです。
しかし伝わらないからと言って完全に放置しておけば、自由気ままで好きなことしかしない、まるで動物のような子どもはそのまま大きくなってしまいます。
そして中学生や高校生、反抗期となったときにきっととんでもない目に会うのは明白‥
やはり習い事1つとっても、すべては教育です。
子どもは毎日毎日ゆっくりと時間をかけながら自我が作られていっているのです。
名著『一流の育て方』から学ぶ継続する意味
ここに一冊の本があります。
『一流の育て方』という本です。
それまで子どもの教育についてそこまで真剣に考えていなかったワタシ。健康で元気に育ってくれれば良いな、と軽い気持ちで捉えていたのですが、小学校に上がりあまりに自由でわがままな娘を見て
「こりゃ将来が不安だ‥‥」
可愛がりすぎるのはこの娘のためにならないとやっと決意
本屋さんでそれっぽい本を物色していたときに巡り合ったのがこの本だったのです。
最初はこんな平凡な我が家のおチビちゃんに対して一流!って、身構えてしまいましたがちょっと立ち読みしたらすっと心に入ってきて、そのまま購入。
冒頭から
長年にわたって何度読み返しても普遍的な教訓を与えてくれる「親の教科書」をコンセプトにしている
というこの掴み。
ケースバイケースが常の子育てにとって、普遍的な親の教科書って良い存在だなと思いました。
またこの本は一流企業、一流大学に進んだ人が幼少期に親から受けた教育のことで感謝していること、またもう少しこうして欲しかったことなどインタビュー形式で掲載されていて読んでいてとてもためになります。
この本、ちゃんとまとめてしっかりとしたレビュー記事としたかったのですが、今回子どもの習い事問題を扱う上で先に登場してもらいました。
そんな名著の中から今日のテーマにばっちりはまるのがこの本の第三章、やり抜く力「グリット」を育むです。
この章では子どもに真剣に挑戦させ、そして簡単にはやめさせないということについて言及されていて、今のワタシにまさにぴったりだったのです。
何事もそうですが、最後まで諦めずにやるというのは1つの立派な才能であり、その人の武器になります。
これは社会に出てもそうで、結果が出ないからと諦めてしまえばそこまでです。
良く言えば臨機応変、すぐ切り替えて新しいことにチャレンジしているとも取れますが、実際「完遂能力」ほど強いものはありません。
結局ちゃんと最初に与えたことをやり遂げる人に、上司は仕事を任せようと判断しますからね。
さてこのグリットを育むために本書が掲げているのが以下のポイント。
モチベーションを高める
真剣に最後まで続けさせる
この2点です。
「一流の育て方」なんてタイトルだからどんな凄い教育方法なんだと読み始めてからしばし不安でしたが、こうやって各項目ごとにわかりやすくポイントを絞って解説してくれているので取り組みやすいです。
早速各ポイントを見ていきましょう。
モチベーションを高める
モチベーション、これほど大事なことはありませんよね。大人だってそうです。社会に出たら毎日同じことの繰り返し、単調な処理に追われ生きる意味すら見失いかけます。
そんなときに自分を鼓舞させるのは《モチベーション》しかありません。
子どもの習い事もそうですね。
子どもにどうやってこのモチベーションを抱かせるのか?そのコツが本書によると
モチベーションを上げる秘訣は「挑戦させる」こと
子どもの応援団になること
子どもに期待を伝えること
だそうです。
確かに‥たしかに当てはまっているかも。
娘も好きなこと、自分からやりだした遊びなんかはほんと見ているこっちがうんざいするくらい真剣に取り組みます。
要はこういうことですよね。
とにかく自発的にやらせてみる、挑戦させてみるということです。
なんとなくうちの娘はこれが向いてるかな?っていう親の判断や近所の友達、仲の良い友達がやっているから、幼少期の習い事にはこれが良いからという情報だけで子どもの選択肢を狭めてはいけないということです。
とにかく挑戦させてみること。
自分から始めたことは最後までやらせてあげるということですね。
書の中でも子どもを「言い出しっぺ」にしてしまうススメが書かれています。
親からの応援ほど子どもを強くすることはありません。
子どもが始めたことで、親にとっては最初は否定的だったことでも、信じて応援してあげるという親の心構えも必要だと説かれています。
おっしゃる通りですね。
そして個人的にはもっとも大きな発見だったのがこの最後のポイント
ちゃんと期待していることを伝えるということです。
これ、今まで親の期待は伝えてはいけないんだと思ってました。特にうちの娘はプレッシャーとかに弱いので少し距離を置いて見守るくらいが良いのかな?と
でも考えてみれば確かにそうですよね、まったく期待されてないことを真剣に取り組むのって難しいですよね。
仕事だってそうです。
つまりこれは子どもに対する考え方という変な固執が招いたことでした。子どもだからってなめてはいけないんです。
これに気づいたとき、ワタシは子どもに対する考え方が変わりました。
あとはいかに続けさせるか?ですね。
この本にも最後まで続けさせることの重要性が書かれています。
真剣に最後まで続けさせる
子どもが習い事を辞めたいと言ってきた我が家にとって、この章のもっとも重要な項目がここです。
先に引用させてもらいます。まさにこの一言なのですが
物事を途中で投げ出すとそれが癖になり、自分で妥協点を勝手に見つけ、すべて中途半端に終わらせてしまう人間になってしまう
これは本の中のアンケートの一文ですが、ワタシが危惧していたのはまさにこれなのです。
確かに嫌々通わされた習い事は何の意味も持たないことはワタシ自身が幼少期に体験してきたわけで、わかっているつもりです。
だから少々甘いかな?と思っても娘がもう辞めたいと言ってきたらちゃんと考えて応えようと思ってました。
しかし、同時にこの「辞め癖」はとても恐い
最後までやりきったあとの充実感を感じて欲しいというワタシの希望もあり、この癖だけは絶対避けたいところです。
じゃあどう続けさせるか?という問題が再燃しますが、もうすでにこの章で答えは用意されていたんです。
ちゃんと応援し、期待を伝える
失敗してもそれを受け止め応援してあげる。
これは親の対応がとても大切な問題なんですね。
でぃすけのつぶやき
小さい頃、とにかく習い事をたくさんやらされました。
水泳、書道、そろばん、学習塾…
遊ぶ暇もなくランドセル置いて通わなければならない状況は当時とても嫌で、結局あの習い事が今の自分のどこに生きているのか正直疑問ではあります。
しかし、自分から習いたいと伝えたピアノは熱意が途切れることなくワタシを自然と音楽の世界に導いてくれました。
仕事にはならなかったけど、今でも音楽仲間と音を作ったりしますし、これは死ぬまで付き合える趣味以上のものになったのは事実です。
やっぱり自分から「言い出しっぺ」になってしまえば、それはもうとことんやりますよね。
娘からそんな申し出があったら、真剣に応援しようと思います。
色々挑戦はさせるけど無理強いはしない
このスタンスが大切かな
色々通わせてくれた両親には、今でこそ感謝できますが…学費とかね…親になるとわかるよね…
 |
一流の育て方―――ビジネスでも勉強でもズバ抜けて活躍できる子を育てる 新品価格 |
![]()